「とか」「ってゆうか」のコミュニケーションと友人関係
関西大学生調査報告書
1.調査の目的
2.調査の概要とデザイン
3.調査結果(1) ─ 8つの若者語の受容実態
4.調査結果(2) ─ 「とか」「ってゆうか」と友人関係
5.調査結果(3) ─ 携帯電話・電子メール利用と友人関係
参考文献 / 付録(調査票と単純集計結果)
調査の概要
この調査は、1998年4月に東洋大学朝霞キャンパス(埼玉県)の大学生を対象に行ったアンケート調査の続編にあたり、そこで得られた知見のさらなる検証と補完を意図して行われたものである。したがって、その主目的は前回と同じく、次に挙げるような若者語の使用と対人関係意識 ―― 特に友人関係に関する ―― との関連を探ることにある。略述しておこう。
1990年代に入ったあたりから、対人関係面において問題化される若者語がいくつか登場してきた。例えば、次のような新聞記事中にみられる「とか」弁、「みたいな」「ってゆうか」などである。(下線は引用者による)
社員教育を専門にする東京・高輪のテンポラリーエデュコンサルトも、この春約百社からの依頼を受けた。……インストラクターの長谷川三紀さん(35)は…若者の「とか」弁に、今年も悩まされた。「コピーとか必要ですか?」「会議とかやるんですか?」「みたいな」「というか」「だったりして」なども多い。いずれも、ものごとを断定せずにそれとなくはぐらかす表現。「斜に構えて、相手に真正面から対することをよしとしない若者の心模様がかいま見える」と長谷川さん。「ビジネスではごまかしの言葉は通用しない」といっても、なかなか直らない。複雑な人間関係から逃げる根本が変わらないと直らないと、思っている。(読売新聞1993年4月22日付朝刊より)
一般的な印象論として、確かにこうした若者語の背後には、「人間関係から逃げる」かのような、「相手に真正面から対することをよしとしない」かのような、対人関係意識が潜在しているように感じられる。それはまた、例えば、対人的関係を忌避して自分の殻に引きこもる「オタク」的若者像や、あるいは、互いに傷つけ合うことに過敏な「マサツ回避の世代」(千石 [1994])、「やさしさの精神病理」(大平 [1995])、より一般的にいえば、傷つくことを恐れて本音を話さず表層的なやりとりに終始する希薄化した人間関係、といった現代若者論の主論調を思い起こさせるものでもある。
しかし、はたしてこれら1990年代に登場した若者語のニューフェイス ――「とか」「ってゆうか」「みたいな」など ―― の背後にあるのは、対人関係から逃げる意識あるいは浅く希薄な表面的な対人関係を好む意識なのだろうか。ことさらにこの点を疑問視するには、二つの根拠がある(詳細は辻[1999b][1999c]を参照)。
一つは、現代の若者の特徴としてしばしば論じられる対人関係の忌避や希薄化、表層化、不活発化などが本当であるか、疑わしいことだ。少なくとも信頼に足るいくつかの社会調査の結果をみる限り、若者の対人関係が希薄化したり不活発になったりした形跡はみられない。むしろ友人の数は増えているし、つきあいが表面的になってもいない。若者の人間関係が希薄化したとか、「オタク」化・孤独化したとかいった論調はある種の錯覚である公算が大きいのである(その錯覚がどこから生じたかは橋元[1998]に述べられている)。
もう一つは、「とか」「ってゆうか」などの若者語を用いることに、話者の本音をぼかして伝わりにくくしたり、会話を表層的なやりとりにとどめおくなどといった積極的な機能があるとはおよそ考えられないことである。それはむしろ発話内容(何を話すか)の選択に関わる問題であり、こうした若者語を用いるか用いないか(どう話すか)の選択に関わるものではない。したがって、これらの若者語の背後に希薄な・表層的な対人関係を想定するのは基本的に筋違いといえる。
むしろ語用論の観点から考えるならば、「とか」「ってゆうか」などのもつ対人関係上の機能の正確なところは、言語行為の設定する対人関係へのコミットメントを弱める・緩める、というものである(この点に関する語用論的分析の詳細は辻[1996][1999b])。言い換えれば、コミュニケーションにおける対人関係に拘束されることを回避する ―― 対人関係そのものを回避するのではなく ―― はたらきである。
以上のことから、弱い仮説(より消極的な仮説)と強い仮説(より積極的な仮説)の二通りを導くことができる。
- 弱い仮説:
- 「とか」「ってゆうか」などの若者語の使用と、希薄な対人関係を志向する意識(その極端な形として対人関係そのものを忌避する意識)とは、結びついていないだろう。
- 強い仮説:
- それらの若者語の使用は、束縛されない対人関係を志向する意識と結びついているだろう。
前者は対人関係の親疎、喩えていえば対人関係の"深い-浅い"または"濃い-薄い"に関わる仮説であり、後者は対人関係の束縛性、その"重い-軽い"に関わる仮説である。
前回の東洋大学生調査では、辻[1999b]に報告したとおり、上記の弱い仮説を支持し、また、強い仮説についても部分的に支持する結果が認められた。「部分的に」というのは、対人関係の"軽さ"に関する心理態度尺度として設定した2項目のうちの1項目(対人関係の切り替え志向)についてのみ、ここで問題としている若者語の使用頻度との間に有意な正の相関がみられた、ということである。
ただ、仮説に肯定的な結果が得られたとはいえ、地域的にも限定された一大学の学生を対象とした調査であり、あくまでケーススタディの域をこえるものではない。そこで、その補足として行ったのが、今回の関西大学生調査である。依然として調査対象が限定されているというサンプリング上の欠点は免れえないが、仮に前回(首都圏)と今回(関西圏)で同様の傾向が認められたとすれば、それはかなりrobustな傾向とみなせよう。
結果としては、弱い仮説については支持が得られ、強い仮説については得られなかった。
今回の調査では、友人関係についての設問を前回より増やし、因子分析を行って友人関係意識の構造を探ってみた。まず、その結果を表1に示す。
表1 友人関係スタンスに関する因子分析の結果
因子負荷量(主成分解、Promax回転後)
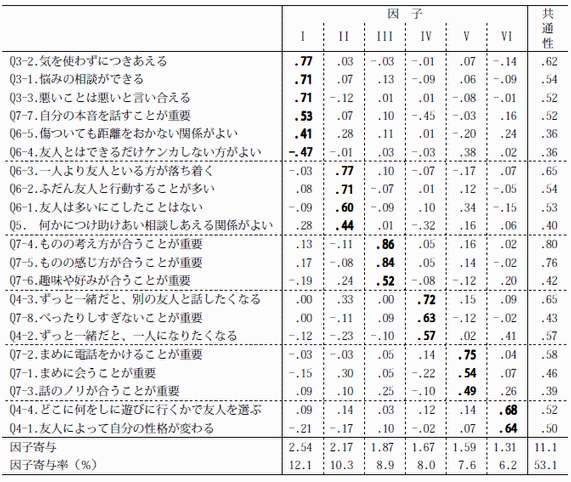
因子負荷量からみて、因子Iは、遠慮なく悩みや本音をぶつけることができ、傷つくことやケンカも許容できる友人関係への志向、“非マサツ回避的親密性”を表す因子と解釈できよう。また、IIは友人との“(集団的)共在”、IIIは友人との“パーソナリティ一致”、IVは友人関係における“脱束縛性”への志向を表す因子として、それぞれ解釈できる。Vは、友人との接触・コンタクトそのもの、コミュニケーションのチャネルを開いておくことを重視する態度であり、Jacobson[1960=1973:p.191]の用語を借りるなら、“交話(phatic)志向”因子と名づけることができよう。VIは、自分を軸にして相手を選び替えるか(Q4-4)・相手を軸にして自分の性格を選び替えるか(Q4-1)の2項目の負荷の大きさで特徴づけられる因子であり、自分の周波数に合わせるか相手の周波数に合わせるかという違いはあるものの、場面や状況に応じて対人的な周波数調整(チューニング)を行うという面では共通性を見いだすことができる。この点で、“対人的チューニング志向”因子と名づけておくことにしたい。
表2は、これら6つの因子得点と「とか」「ってゆうか」などの若者語(=α群)の使用頻度との相関係数を示したものである(数値はSpearmanの順位相関係数)。なお、β群は、対人関係上の語用論的機能をもたない若者語「めっちゃ(超)」「キレる」などであり、α群との比較対照のために設問した。
表2 若者語α群・β群の使用頻度と友人関係スタンス因子との相関
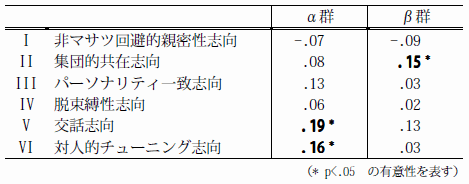
ここに示されるとおり、「とか」「ってゆうか」などの若者語(α群)の使用頻度は、因子Iの非マサツ回避的親密性志向とは有意に相関しておらず、したがって、希薄な・表面的な友人関係への志向とは結びついていない。これは弱い仮説を支持する分析結果と言えるだろう。
一方、因子IVの脱束縛性志向とも無相関であり、したがって、強い仮説についてはひとまず支持する結果が得られなかった。むしろ、因子Vの交話志向、因子VIの対人的チューニング志向との間に有意な正の相関が認められる。また、これらについては、β群の若者語の使用頻度とは有意な相関がみられないことから、若者語一般の傾向ではなく、α群の若者語(つまり対人関係上の語用論的機能をもつ若者語)に特殊な傾向とみなしうる。
この結果について、あえて解釈をほどこせば、次のように考えられなくもない。
交話志向とは、相手とつながっていること、コミュニケーションのチャネルを維持しておくことそのものを重視する態度である。設問レベルでみても、この交話志向を端的に表すQ7-1(まめに会うことが重要)・Q7-2(まめに電話することが重要)は、α群の若者語の使用頻度とかなりはっきりした相関傾向を示している(Spearmanの順位相関係数にしてそれぞれ.26と.25、いずれもp<.001、β群の若者語の使用頻度とは有意な相関水準にない)。ここで、α群の若者語の語用論的特性にたちかえって考え直してみるならば、それらは言語行為の設定する対人関係へのコミットメントを弱める機能を有するものであった。つまり、ある見方をすれば、それらはコミュニケーションにおける社会的行為の交換・応接という性格を弱めるはたらきをするわけだ。その結果として、相対的にコミュニケーションにおける交話的側面が強調される。α群の若者語の使用と交話志向とをつなぐ糸は、この点に求められよう。
対人的チューニング志向とα群の若者語の使用とをつなぐ線についても、同様の考え方が可能である。対人的周波数の同調という観点からみれば、コミュニケーションは行為の交換・応接の場ではなく、対人的共鳴・共振の場ということになる。因子IIIのパーソナリティ一致志向との区別に留意するならば、相手の内実への共鳴・共振ということではなく、その場その場での共鳴・共振そのものへの志向である。いわば、カラオケでその場にいる者がリズムとメロディを介して一体感をもつようなものといえるだろうか。そのとき、歌や歌詞というのは、情報や行為の伝達媒体ではなく、ある種の共鳴・共振の媒体となっている。α群の若者語を用いることは、コミュニケーションにおける行為の交換・応接の場という性格を弱め、相対的にこうした共鳴・共振の場という性格を強める、とも考えうる。
さて、前回調査では、友人関係の切り替え志向(Q4-4「どこに何をしに行くかによって友人を選ぶ」)と携帯電話・PHSの所有状況との間に有意な関連が認められたが、今回の調査でも、この点については共通の傾向が認められた。友人関係の切り替え志向が強いほど、携帯電話・PHSで友人に電話をかける頻度が高く、また友人の電話番号のメモリ登録数も多い(いずれもSpearmanの順位相関係数にして.19, p<.05 )。友人数との相関を考慮しても、これらの偏相関値は有意な水準を保つ。友人関係の切り替え志向は携帯電話・PHSの利用と親和的であり、どうやら若者にとって携帯電話・PHSは、友人とのコミュニケーションのチャネルを気軽に切り替えることのできるある種の「リモコン」になっているようだ。
文献
- 橋元良明 1998 「パーソナル・メディアとコミュニケーション行動」,竹内郁郎ほか編『メディア・コミュニケーション論』,北樹出版
- Jacobson,R. 1960 Closing Statement: Linguistics and Poetics, T.A.Sebeok(ed.), Style in Language, Technology Press of Massachusetts Institute of Technology. =1973 八幡屋直子訳「言語学と詩学」,川本茂雄監修『一般言語学』,みすず書房
- 大平 健 1995 『やさしさの精神病理』,岩波書店(岩波新書)
- 千石 保 1994 『マサツ回避の世代』,PHP研究所
- 辻 大介 1996 「若者におけるコミュニケーション様式変化」,『東京大学社会情報研究所紀要』51号,pp.42-61
- 辻 大介 1999a 「「とか」弁のコミュニケーション心理」,『第3回社会言語科学会研究大会予稿集』,pp.19-24
- 辻 大介 1999b 「若者語と対人関係
- 辻 大介 1999c 「若者のコミュニケーションの変容と新しいメディア」,橋元良明編『子ども・青少年とコミュニケーション』,北樹出版