若者の親子・友人関係とアイデンティティ
―― 16~17歳を対象としたアンケート調査の結果から
1.はじめに
2.調査の概要
3.自己意識に関する諸項目の連関と男女差
4.自己意識と親・友人との関係
5.まとめに代えて
註 / 文献 / Abstract
抄 録
本稿では、2002年3月に首都圏30km内在住の16~17歳を対象におこなったアンケート調査のデータをもとに、アイデンティティ(自己)意識と親子・友人関係との関連について分析する。結果としては、自己像が明確につかめないアイデンティティ不定型が50%、複数の自己像をもつ多元型が36%、単一の自己像をもつ一元型が14%であること、女性に不定型が多く一元型が少ないこと、不確定型の者は対人関係の満足度や被理解感、信頼感などが低く、家族(親)を疎隔するようなコミュニケーション・ツールとして携帯電話を用いていること、多元型の者は一元型と同程度に安定的な対人関係(特に親子関係)を保っているが、電子的なコミュニケーションへの親和性は一元型より高いこと、などが明らかになった。
1.はじめに
社会学的な自我論においては、自己(のアイデンティティ)は、独立自存的なものではなく、他者との関係において形成されるものとされる。本稿は、その基本的観点にならって、若者のアイデンティティ意識が、対人関係――なかでも彼ら彼女らにとって重要な他者である親・友人との関係――およびコミュニケーションとどのように関連しているかを、調査データに基づきつつ検討する。
まず、問題の背景を略述しておこう。
一般に発達心理学においては、青年期は、親から情緒的に独立して、同性の友人や異性の恋人と親密な関係を築くとともに、アイデンティティ(自己同一性)を確立する時期として位置づけられてきた(斎藤[1996]など)。裏を返すなら、青年期とはどの社会・時代においても(少なくとも近代社会以降であれば)、親子関係や友人関係に葛藤や問題を生じやすく、アイデンティティの不安定な時期ということになる。
その一方で、日本の青年・若者のアイデンティティや自己意識、および対人関係の時代的変化を指摘する声もしばしば聞かれるようになった。1970年代に小此木啓吾の唱えた「モラトリアム人間」論は、その嚆矢といえるだろう。
小此木[1978→1981]は、E.H.エリクソンのアイデンティティ論を引きながら、青年期を社会的義務や責任を猶予されるモラトリアム期間と位置づけたうえで、現代社会ではそれが延長され、法的・社会的には成人に達していても、心理面ではモラトリアム状態を保ち続ける若者が目立つようになったとする。彼ら彼女らを特徴づけるのは「古典的なモラトリアム心理」と区別される「新しいモラトリアム心理」であり、その変化を小此木は“半人前意識から全能感へ”“自己直視から自我分裂へ”“自立への渇望から無意欲・しらけへ”などの点にまとめている。それをもとに、より具体的に描きだされる「モラトリアム人間」の像は、次のようなものだ。
何事に対しても、その時その所における当事者であることを避ける。自分はその時とところであくまでも仮の存在であり、“本当の自分”はそっと棚上げしておく。いつでも立場をかえ、考えをかえ、自分自身をも変身させる余地をのこしておく。一貫した主義主張をもたないか、もたないふりをする。特定の党派、集団にすべてを賭けることを避ける。 (p.14)
①まだいかなる職業的役割も獲得していない。②すべての社会的かかわりを暫定的・一時的なものとみなしている。③本当の自分はこれから先の未来に実現されるはずで、現在の自分は仮のものにすぎないと考えている。④すべての価値観、思想から自由で、どのような自己選択もこれから先に延期されている。⑤したがって、すべての社会的出来事に当事者意識をもたず、お客さま意識しかもとうとしない。 (p.30)
ここで指摘されているモラトリアム人間のアイデンティティの特徴は、おおまかにいって次の2点にまとめられるだろう。1つは、「本当の自分」がつねに留保され、未来へと先送りされること、もう1つは、現在の「仮の自分」は状況や関係に応じて変わりうる複数的・多元的なものであることだ。
前者はいわゆる「自分探し」「私探し」へのつながりを、後者は「多重人格」(解離性同一性障害)へのつながりを感じさせるものだが、興味深いことに、1990年ごろからこれらへの文化的・社会的注目が高まりをみせている。朝日新聞の記事データベースで検索したところでは、「自分探し」が見出しに初めて用いられたのは1989年であり、一方、「多重人格」の登場する小説やテレビ番組などがヒットしたのも1990年代の初めである1)。
香山リカ[1999]は、「私探し」について論じた著書のなかで、この多重人格ブームを「もうひとりの私」探しとして読み解いている。多重人格の症例は、アメリカで1970年代から急増し、日本でもやはり近年増えているという(大澤・斎藤[2000:p.80-81])。このような症例の増加および文化・社会的関心の高まりについて、東浩紀[2001]は「私たちの社会そのものが、何かしら多重人格的なモデルを強く求めてきたから」(p.168)であるとし、今日のオタクにみられるようなポストモダンの人間像(「データベース的動物」)と、多重人格的な自己感覚を関連づける議論をおこなっている。
社会学の分野でも1990年代の後半に、自己の多元性に着目した議論があらわれ始めた。浅野智彦[1999]は、東京・神戸の16~29歳を対象におこなわれた1992~93年のアンケート調査の結果から、因子分析によって3種の友人関係志向を抽出している。そのうちの1つ、「相手やつきあいの程度に応じて関係のあり方が変わっていく」状況志向の因子得点は、「場面によってでてくる自分というものは違う」「どんな場面でも自分らしさを貫くことが大切だ」「自分がどんな人間かわからなくなることがある」「自分には自分らしさというものがあると思う」などの自己意識と有意に相関していた。浅野はこの分析結果を解釈して、状況志向型の人にとっての自己とは、「ひとつの自己イメージによってはとらえきれないものであり、場面ごとに出てくるいくつもの自分のどれもがそれぞれに自分らしいのである」とし、「複数の自分のどれもが本当の自分であるというような」多元的な自己のありようを示唆している(p.46-47)。
こうした浅野の見解の特徴は、モラトリアム人間論が「本当の自分」「仮の(偽の)自分」という二項対立を前提としていたのに対して、その区別の適切性を疑問視したこと、そして、「本当の自分」を単一的でなく多元的なものでありうると考えなおした点にある。
私自身もまた、浅野とは別の文脈から、現代的な自我構造として複数の identities がゆるやかに束ねられたかたちのものを提示したことがある(辻[1999])。1970年代以降の対人関係の変化として、経年的な社会調査データの追跡から浮かび上がってきたのは、いつでも・どこでもつきあいを保つような包括的な対人関係が敬遠され、つきあいの範囲をけじめづけるような限定的な対人関係が好まれるようになってきたことだ。これはいわゆる関係の「希薄化」を思わせるが、一方で、「心の深いところは出さずにつきあう」といった傾向が強まった形跡はなく、また、対人関係面での充実感は低くなるどころか高まっていた。限定的な対人関係は、孤独感や虚無感に彩られた希薄な関係とは区別されるべきものであり、むしろ関係の充実感につながるようなのだ。
さらに、1998年におこなった学生調査の分析結果からは、限定的な対人関係志向の一種として位置づけた“関係切り替え”志向(設問文は「どこに何をしに遊びに行くかによっていっしょに行く友だちを選ぶ」)と、携帯電話の利用率や新しい特徴をもつ若者語の使用度とのあいだに有意な相関が認められた。つまり、若者にみられる現代的なコミュニケーション・スタイルも、部分的な対人関係への志向に関係していたのである。
これらのことを総合的に解釈するために提出したのが、図1のような「自我構造の模式図」だ(同上書:p.23)。
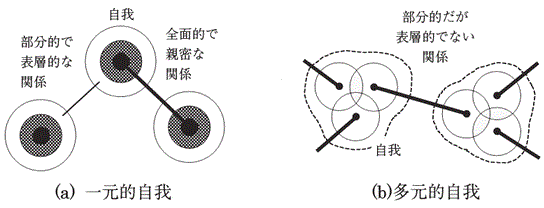
図1 自我構造の2つの模式図
(a)のような同心円上の自我をイメージするなら、その中核から離れた「部分」をもってするつきあいは、すなわち、「心の深いところ」や「本音」を隠した表層的で希薄な対人関係を意味することになるだろう。しかし、(b)のように、複数の中心をもち複数の円がゆるやかに束ねられた自我構造――多元的なidentities――をイメージするなら、部分的な関係は同時に表層的でない関係でありうる。そして、こちらのほうが対人関係志向の経年的変化を矛盾なく説明でき、また、関係フリッパーの自己図式にもよりふさわしい。というのは、その後の調査でも、ほぼ一貫して、携帯電話利用は関係切り替え志向と有意に相関するのに対し、関係の表層性や希薄性とは相関がみられないからだ。
また、辻[1999]では、校正段階で編集上の都合により削除されてしまったため、ふれられていないのだが、関係切り替え志向と、相手によって自分の性格が切り替わる傾向(設問文は「話をする相手によって自分の性格が変わる」)とのあいだには、0.1%水準の有意な相関(順位相関係数ρ=0.21)が確認されていたのである。
以上でみてきたような、対人関係の切り替え志向化・状況志向化、および自己の多元化が、ここ数十年間で実際に進行してきたのか、現時点でははっきりしたことは言えない。
本稿では、多元的自己(複数のアイデンティティ)という新しい視角を引き継ぐにとどめ、青年期におけるアイデンティティの拡散・ゆらぎという旧来の観点とともに、若者のアイデンティティおよび対人関係の現状を探ることにしたい。
2.調査の概要
今回のアンケート調査は、首都圏30km内に在住し、親と同居する16~17歳(調査時点)を対象におこなった。層化2段無作為抽出法によって選びだした800人に対して、2002年3月に調査票を郵送で配布・回収した。有効標本数は387票(有効回収率48.4%)。調査方法の詳細および結果概要については、辻[2003]を参照されたい。
自己意識に関する設問と単純集計結果は、表1のとおり。
表1 自己意識に関する設問項目と単純集計結果
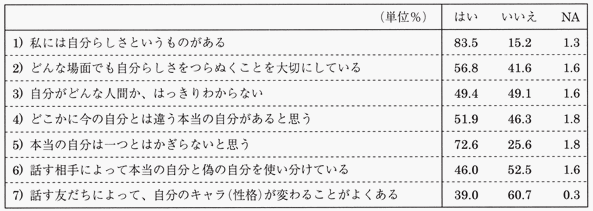
7)の設問以外は、浅野[1999]などの知見と関連づけるため、彼の所属する青少年研究会[2001]のアンケート調査の設問を参照した。なお、7)については「はい/いいえ」ではなく、対立する選択肢(「どんな友だちと話しても、自分のキャラ(性格)はほとんど変わらない」)との2択式の設問である。
これまでに青少年研究会とそのメンバーは、上記の設問を用いた調査研究をいくつかおこなっている(東京・神戸の16~29歳を対象とした川崎ほか編[1995]、首都圏の4大学を対象とした青少年研究会[2001]、高校生を対象とした岩田[1999][2000]など)。いずれの調査でも、自己意識の関連項目として、友人関係の設問はなされているものの、親子関係についての設問はないことが、本稿の調査との最も大きな相違点である2)。
3.自己意識に関する諸項目の連関と男女差
では、今回の調査結果の分析にとりかかるとしよう。まず、自己意識に関する諸設問の肯定回答率を男女ごとに示したものが、表2である。
表2 自己意識の男女差
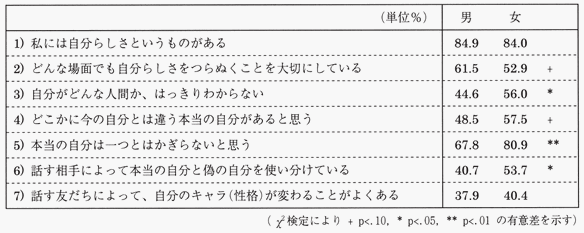
「1)自分らしさがある」と答えた者は男女ともに8割を超えており、大半は何かしらのアイデンティティ感覚をもちえているといえるだろう。一方で「3)自分がどんな人間か、はっきりわからない」者も5割前後にのぼるため、必ずしも自らのアイデンティティが明確につかめているわけではない。この自己像の不明確感は女性に多く、そのためか、「4)どこかに今の自分とは違う本当の自分がある」という“仮の自分”感覚も女性でやや多くなっている。また、女性の方が「6)本当の自分と偽の自分を使い分けている」者も、「5)本当の自分は一つとはかぎらない」という多元的自己感覚のもちぬしも多く、「2)自分らしさをつらぬくことを大切にしている」という一貫主義者はやや少なくなっている。アイデンティティの拡散・動揺という観点からみるにせよ、複数・多元的なアイデンティティという観点からみるにせよ、その傾向は女性に強いようだ。ただし、対する友人によって「7)自分のキャラが変わる」というキャラクター切り替え志向には、男女差がみられない。
このような男女差を考慮しつつ、便宜的に性別を制御変数として、自己意識に関する諸項目間の偏相関値r’を計算してみた。その結果が表3である。ちなみに、男女ごとの相関値も算出してみたが、相関パターンは基本的によく類似していた。
このうち、1)と2)の相関は論理的に当然であるが(「2)自分らしさをつらぬく」ためには、まず「1)自分らしさというものがある」ことが前提になる。実際、2)を肯定し1)を否定するという論理矛盾した回答者は8名にすぎず、誤差の範囲内とみなせるものであった)、それ以外の相関傾向についても常識的にうなずけるものが多い。おおまかに傾向をまとめると、自己像の不明確な者は、やはり自分らしさの感覚をもちにくく、自分らしさの一貫性も乏しい。また、“仮の自分”感覚が高く、本当/偽の自分を使い分ける者が多い。
友人に対するキャラクター切り替え志向についていえば、多元的自己感覚、本当/偽の自分の使い分け、ともに有意な正相関がみられるが、後者の相関値のほうが高く、相手によって自己呈示が変わるのは、複数の(本当の)自己よりむしろ、仮面的な役割演技をする/しないの面がより大きいようだ。
表3 性別を制御変数とした自己意識諸項目間の偏相関値
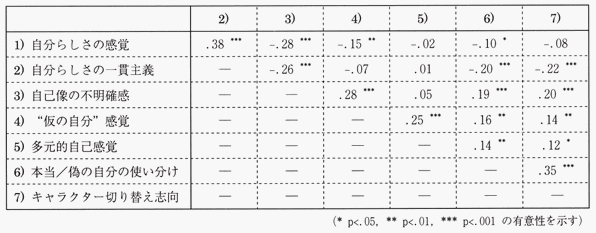
さらに注目したいのは、「5)多元的自己感覚」と「2)自分らしさの一貫主義」「3)自己像の不明確感」に、相関がみられないことである。つまり、自己が多元的に感じられるからといって、必ずしもアイデンティティの動揺や拡散につながるわけではない――多元的でありつつも安定した identities を保ちうる――ということだ。
ここで便宜的に3)を肯定回答した場合をアイデンティティ“不定型”、3)を否定・5)を肯定した場合を“多元型”、両者とも否定した場合を“一元型”とすると、その分布は表4のようになる。男女間にはχ2検定によりp<.01の有意差が認められたが、これは女性にアイデンティティ不定型が多く、一元型が少ないことによる。多元型の比率は男女でほとんど変わらず、今回の調査ではおよそ3人に1人がこのタイプにあたる。彼ら彼女らは、アイデンティティの拡散・動揺という旧来的な観点からは見逃されがちな層であると言っていいだろう。
表4 アイデンティティの類型分布
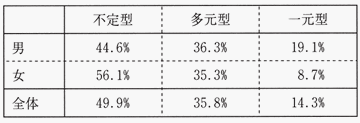
これらの3類型による自己意識の差をみたものが、表5である(数値はそれぞれの設問に肯定回答した率:χ2検定によりすべての項目についてp<.001の有意差)。多元型のアイデンティティを有する者は、一元型と同水準の自分らしさの感覚をもち、また、自分らしさの一貫主義は一元型よりむしろ高くなっている。この点をみても、多元型は一元型と同様の安定したアイデンティティとみなすことができ、不定型(アイデンティティの未確立)とは区別されるべきものと言えるだろう。ただし、“仮の自分”感覚や、本当/偽の自分の使い分けについては、不定型と一元型の中間にあたる値が示されており、これらの面では一元型よりアイデンティティの不安定につながるところもあるようだ。
表5 アイデンティティの類型と自己意識の関連
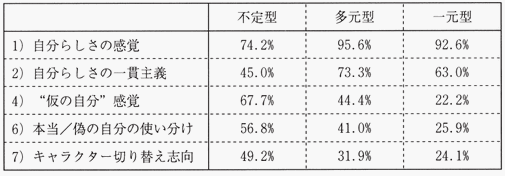
4.自己意識と親・友人との関係
つづいて、性別を制御変数として、自己意識7項目と、親・友人との関係についての設問との偏相関値を算出した結果を、表6に示す。(表中で、“共通感”に対応する設問文は「ものの考え方や感じ方が似ている」、“被理解感”はその相手が「私の考え方や感じ方をよく把握している」、“信頼感”は「どんな困ったことでも、きっと助けてくれる」、“「友だち親子」感”は「親というより友だちのような存在だ」、“関係切り替え志向”は「場合に応じて、いろいろな友だちとつきあうことが多い」、“ディスタンシング志向”は「プライベートなことには深入りしたくない」、“マサツ回避志向”は「互いを傷つけないようにできるだけ気を使う」、“ノリ志向”は「重要なのは話の中身よりノリが合うこと」)
自分らしさの感覚がある者は、親・友人に対する被理解感や関係満足度が高い傾向にあるが、その自分らしさが明確な自己像を結ぶかどうかになると、友人関係面では有意な相関があまりみられず、むしろ親とのあいだで被理解感や信頼感が得られるかどうかがポイントになるようだ。また、仮の自分感覚をもつ者や、本当/偽の自分を使い分ける者は、やはり親・友人との関係満足度がいずれも低い傾向がみられる。
ひとつ興味深いのは、多元的な自己感覚が、母親・父親との「友だち親子」感覚と相関していることだ。複数の自己の並立は、同質(フラット)化した対人関係の並立と結びつくものなのかもしれない。
表6 自己意識と親・友人との関係の偏相関値(制御変数:性別)
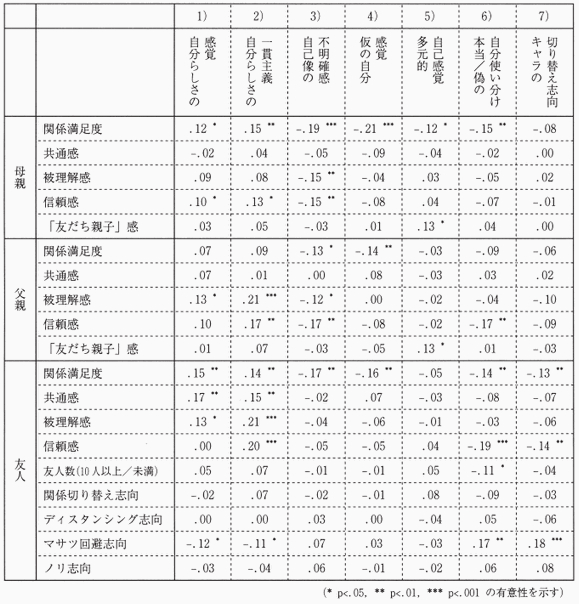
次に、自己意識7項目と、親・友人とのコミュニケーション状況の偏相関値を計算した結果が、表7である。
自己像の不明確な者は、親に対して番通選択(携帯電話にかけてきた相手の表示をみて出るかどうかを選ぶ行動)をおこなうことが多く、友人と「対面では話しにくいことでも、電話でなら話しやすい」「メールでなら書きやすい」という電子的コミュニケーションへの親和性が強い傾向にある。また、携帯電話の効用として、「親が電話をとりつぐことがなくなって、友だちのことが親に知られなくなった」「家族といるときでも、友だちと話すことが増えた」を挙げることが多く、家族を疎隔するツールとして携帯電話を用いている形跡がみられる。同じことは、“仮の自分”感覚をもつ者、本当/偽の自己を使い分ける者についても、おおよそあてはまると言えるだろう。
表7 自己意識と親・友人とのコミュニケーションの偏相関値(制御変数:性別)
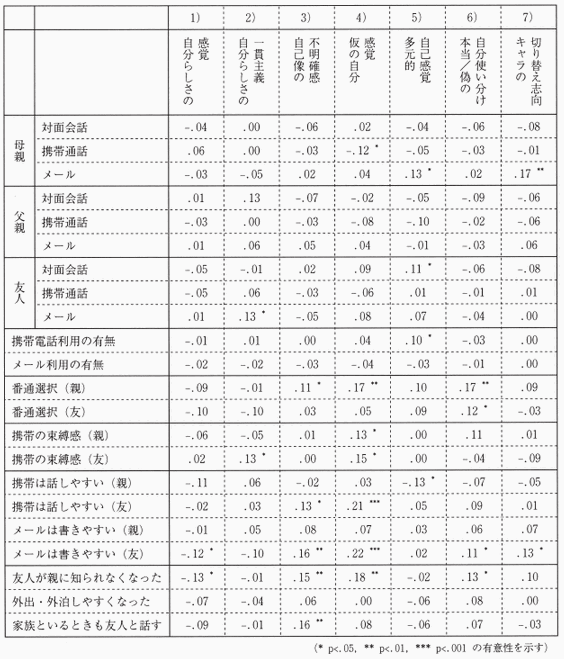
最後に、前節でふれたアイデンティティの3類型と、親・友人との関係およびコミュニケーション状況の関連を、表8にまとめておく(有意差が認められたもののみを抜き出した。数値はそれぞれの設問に肯定回答した率。携帯電話・メール利用に関する設問については、それぞれ利用者を100%とした比率)。
アイデンティティ不定型は、親子関係・友人関係のいずれについても、満足度や被理解感・信頼感などが概して低く、また、友人に対する場合に対面よりも電子的コミュニケーションに親和的で、携帯電話によって家族(親)を疎隔する傾向がみられる。
多元型も、友人との電子的コミュニケーションには親和的だが、親との関係満足や被理解感・信頼感は高く、携帯電話によって家族(親)を疎隔する傾向も不定型よりは弱い。
表8 アイデンティティの類型と、親・友人との関係・コミュニケーション
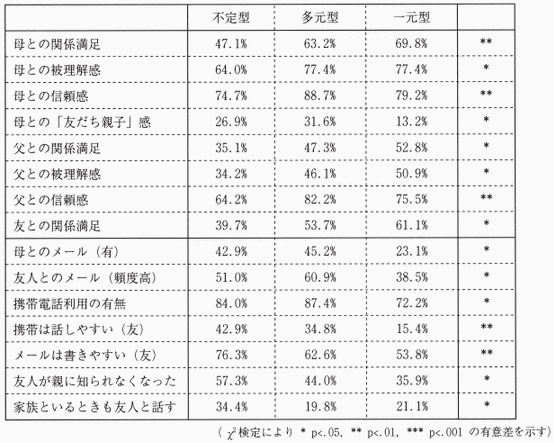
5.まとめに代えて
以上の分析からうかがえるのは、多元型のアイデンティティ(複数の自己の並立)が、従来想定されてきたようなアイデンティティの拡散や動揺(自己の未確立)とは、やはり区別されるべきものということだ。多元型のアイデンティティを有する者は、対人関係、特に親子関係における満足度や被理解感・信頼感が、一元型と同程度かそれ以上に高い。そのことが複数の自己に拡散することなく、安定した identities に束ねられていることにつながっているのかもしれない。一方で、一元型よりも電子的なコミュニケーションに親和的な傾向がみられるが、それが何によるものなのかは、今後の検討に委ねざるをえない。
その他にも今後の検討課題は多い。最も重要なのは、多元的自己についての理論整備であり、また、それに基づく実証方法の彫琢である。今回の設問にせよ、はたして「本当の自分は一つとはかぎらないと思う」という文案が多元的自己を測りうるものになっているかどうかには留保を要するだろう。ある種の一般論として「本当の自分は一つとはかぎらない」と考えていたとしても、実際の行動面や対人関係面では一元的な自己呈示をおこなっているかもしれない。たとえば、キャラクター切り替え志向との相関が低い値にとどまるところをみても(表3)、その可能性は少なくないように思える。
また、今回の調査では、1節で紹介した辻[1999]の大学生調査の結果とは異なり、性格(キャラクター)切り替え志向および多元的自己感覚と、関係切り替え志向とのあいだに有意な相関は認められなかった(表6)。これは、対人関係の状況志向性と自己(意識)の多元性を関連づけて論じた浅野[1999]とも食いちがう結果である。この点についても今後のさらなる実証的検討をまたねばならないが、浅野[1999]は有効回収率の面でサンプルに偏りがあることを予想させ、辻[1999]は無作為抽出によらない調査であるため、一部の特殊な層にみられる傾向である可能性が残る。
橋元[2003:p.51]の言うように「日本人の自我構造(定義によるが)がわずか20年の間に大きく変化したり、コーホート(世代)によって大きく違った位相をみせたりするかどうか」という批判も当然考慮しなくてはなるまい3)。いずれにせよ、自己やアイデンティティの多元性についての研究は緒に就いてから日も浅く、今後のさらなる研究の蓄積がまたれる。
本研究は、平成13年度関西大学重点領域研究助成金(研究課題「家族や地域社会における人間関係に見られる倫理観・価値観の変化」・研究代表者:高木修社会学部教授)によって行われた。
註
- 1) テレビ番組としては『ツイン・ピークス』がその嚆矢だろう(アメリカでは1990年に放送され、日本ではその1年後に放送開始)。92年には、フジテレビがそれを真似たとおぼしき『あなただけ見えない』を放送(当時の人気タレントである小泉今日子・三上博史の主演)。同年、ダニエル・キイスの小説『24人のビリー・ミリガン』が翻訳出版され、ベストセラーとなる。
- 2) また、川崎ほか編[1995]以外の調査は、いずれも有意抽出によるサンプリングであるため、この点で結果の信頼性に欠ける面がある。川崎ほか編[1995]の調査についても、多段無作為抽出という信頼性の高いサンプリング手法が採られているものの、設問が多岐にわたるためか、有効回収率は22.3%にとどまっており、この点でやはり調査結果の信頼性にやや欠けるところがある。
- 3) 私自身は、仮に「わずか20年の間に」自我構造の変化があったとしても、それは図1の(a)から(b)への急激な全面的変換ではなく、それらを両極として(a)の同心円がゆるやかにほどけ、(b)に近づいていくような漸次的な変化だろうと考えている。
引用文献
- 浅野智彦 1995 「友人関係における男性と女性」、川崎賢一ほか編『都市青年の意識と行動』恒星社厚生閣
- 浅野智彦 1999 「親密性の新しい形へ」、富田英典・藤村正之編『みんなぼっちの世界』恒星社厚生閣
- 東浩紀 2001 『動物化するポストモダン』講談社現代新書
- 橋元良明 2003 「若者の情報行動と対人関係」、正村俊之編『情報化と文化変容』ミネルヴァ書房
- 岩田考 1999 「友人関係の現在」、『モノグラフ・高校生』56号、ベネッセ教育研究所、pp.32-51
- 岩田考 2000 「高校生の自分探し」、『モノグラフ・高校生』60号、ベネッセ教育研究所、pp.36-49
- 香山リカ 1999 『〈じぶん〉を愛するということ』講談社現代新書
- 小此木啓吾 1978 『モラトリアム人間の時代』中央公論社(→1981 中公文庫版に再録)
- 大澤真幸・斎藤環 2000 「「多重人格」の射程」、『ユリイカ』32巻5号,pp.80-103
- 斎藤誠一 1996 「青年期の人間関係を理解するための基礎」、斎藤誠一編『青年期の人間関係』培風館
- 青少年研究会(編) 2001 『今日の大学生のコミュニケーションと意識』
- 辻大介 1999 「若者のコミュニケーション変容と新しいメディア」、橋元良明・船津衛編『子ども・青少年とコミュニケーション』北樹出版
- 辻大介 2003 「若者の友人・親子関係とコミュニケーションに関する調査研究 概要報告書」、『関西大学社会学部紀要』34巻3号、pp.373-389
Abstract
I conducted a questionnaire survey of 16 and 17 year-olds in Tokyo metropolitan area in March 2002. This paper analyzes the data and reports correlations between the adolescents' images of the self and interpersonal relationships with parents and friends. The main findings are as follows; 50% have an obscure image of the self, 36% have an image of the plural selves, and 14% have an image of the singular self; Compared with males, more females have the obscure identity and less have the singular identity; Obscure identity correlates negatively with interpersonal feelings of satisfaction and understanding; Those who have the plural identities keep stable relationship with friends and especially parents, and their preference of mediated communication via mobile phone and email is stronger than those who have the singular identity.
Daisuke TSUJI, 2004
Young People's Identities in Their Relations with Parents and Friends:
An Analysis of Questionnaire Survey Data of 16 and 17 year-olds
The Bulletin of Faculty of Sociology, Kansai University, Vol.35-No.2, pp.147-159