※以下は『月刊高校教育』に掲載されたものです: » PDFダウンロード
「対話」から「共話」へ
若者のコミュニケーション作法の現在形
若者のことばづかいは、年長者から何かと目の敵にされることが多い。なかでも、敬語がうまく使えないことと並んで、従来からあることばが違った意味で用いられることが、しばしば槍玉にあげられる。一例を紹介しよう。
「○○くん、やばいよ、超かっこいー!」
どうして「かっこいい」のに「やばい」のか? 「やばい」は悪い意味をもつのではなかったのか? 「やばい」をほめことばで使うとはどういうことだ? 今どきの若者はことばもろくに使えんのか?!
年配の方々からは、こんなお小言も聞こえてきそうだ。しかし、「ことばの乱れ」を嘆く声は、平安時代からあった(興味ある方は『枕草子』を改めて読んでみてほしい)。いつの時代にも、ことばは移ろいゆく。その変化が年長世代には(清少納言ほどの知識人であっても)「乱れ」にみえてしまうのである。
秋月高太郎氏の『ありえない日本語』(ちくま新書)によれば、「やばい」をはじめとする現代の若者ことばにも、ちゃんとした一定の用法とルールがあるという。だとすれば、まず必要なのは、若者ことば――および若者そのもの――を「乱れ」ていると白眼視したり矯正したりすることではなく、そのルールを理解することであるだろう。そこで以下では、「ありえない」という若者ことばを手がかりにして、秋月氏とも少し違った視点から、若者のコミュニケーションの作法がどのようなものであるかを探ってみることにしたい。
* * *
「ありえない」は従来、現実に起こるはずのないできごとを表すのに用いられてきた。たとえば、「人間が永遠に死なないことはありえない」というように。それに対して、最近の若者ことばでは、次のように、現実にすでに起こった・(目の前で)起きているできごとに対しても用いられる。
「今から抜き打ちテストをします」
「えーっ、ありえなーい」
これを聞いて、”現実に目の前でテストをすると言っているのに、「ありえない」とは何ごとか”とカチンとくる気持ちは私にもよくわかる。現実世界で起きていること(自分が現実に起こしたこと)を、手前勝手に否定されたような気がするからだ。
しかし、この「ありえない」は、現実世界について何かを述べようとするものではない。むしろ、話し手の想定する仮想世界のなかでは、抜き打ちテストは「ありえない」ことを表現するものなのだ。つまり、いわゆる想定の範囲内か外かについて述べているのであり、「ありえない」の適用範囲が、現実世界だけでなく(話し手の)仮想世界にまで拡張されているのである。
さて、このような場合、少し前までは「えーっ、信じらんなーい」と言われていたことだろう。こちらのほうがことばの用法という面では抵抗感が少ないかもしれないが、それ以上に、「ありえない」と「信じられない」では、その意味あいが少なからず異なってくるところがある。たとえば、次の(a)と(b)を比べてみよう(この「ありえない」は、とりあえず従来の用法に則ったものと考えてもらいたい)。
(a) 彼が万引きするなんて、信じられない
(b) 彼が万引きするなんて、ありえない
(a)が表現しているのは、あるできごと(彼の万引き)に対する話し手の心理状態(信じられるか否か)であり、そのできごとが事実であるか否かについては、さしあたり何も言っていない。だから、「彼が万引きをしたのは紛れもない事実だが、私には信じられない」という言い換えも成り立ちうる。一方、(b)は、そのできごとを端的に否定するものなので、「彼が万引きをしたのは紛れもない事実だが、ありえない」と言い換えると、ナンセンスな表現になってしまう。この(a)と(b)の違いを簡単に図式化すると、次のようになる。
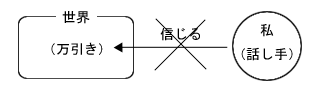
(a) 信じられない
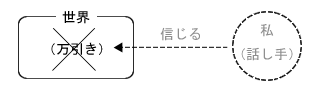
(b) ありえない
この図からもわかるように、”信じる”などの心のはたらきを担う主体、つまり〈私〉が、「ありえない」の表現する構図のなかでは消え去っている。というより、そのような主体や心のはたらきは、世界のなかに溶けこんでいると言ったほうがいいかもしれない。ある風景を見たときの心の動き(感動)が世界に溶けこんで、その風景の美しさとして表現されるように、彼の万引き(や抜き打ちテスト)を信じられないことは、そのできごとのありえなさとして表現されるのである。
* * *
世界から独立・自立した主体の消失あるいは融解。よりくだけた言い方に直せば、〈私〉が思いや考えを世界から切り離し、前面に押しだすことをしない表現スタイル。このようなコミュニケーションの作法は、「ありえない」とはまた別のかたちで、若者ことばのあちこちに見られる。
たとえば、「とか」「てゆうか」「みたいな」「って感じ」などの、いわゆるぼかしことばは、〈私〉の断定的な語り口をやわらげ、相手への押しつけがましさを軽減しようとする。いちいち相手にあいづちを求めるような「~じゃないですか」の多用なども、〈私〉の主張を前面に押しだすのではなく、相手の了解をくみ入れる作法と考えられる。
つまり、これらの若者ことばが用いられるコミュニケーションにおいては、話し手の〈私〉は相手との対話世界のなかに溶けだしているのだ。いや、それは相異なる〈私〉と〈私〉の対峙する「対話」の世界というよりむしろ、新聞記者の織井優佳氏が名づけたように、後景化された〈私たち〉が共に織りなす「共話」の世界と呼んだほうがよいものかもしれない(朝日新聞1999年4月19日付朝刊)。
しかし、私自身もそうだが、年長世代はこうした若者ことばに相手への配慮を感じとるより、むしろ苛立たせられてしまうことだろう。なぜなら、それが過度な無用の配慮に思えるからであり、自分への自信のなさ・主体性のなさの現れに見えるからだ。ここに、「対話」世代と「共話」世代のジェネレーション・ギャップがある。
* * *
「共話」世代は、身近な人間関係、なかでも友人関係への志向が強い。さまざまな若者調査の結果をみても、この2~30年で友人数は明らかに増加傾向にあり、友人関係の満足感や充実感も上昇している。その一方で、友人であってもうわべだけでつきあうようになったのではないかという関係の表層化・希薄化を指摘する声もあるが、日経産業消費研究所の若者調査によれば、「何の隠しだてもなくつきあう」という回答が1980年代から一貫して6割前後で、ほとんど変化はない。NHKの中高生調査でも同様である。私の属する研究グループが2003年におこなった全国調査でも(研究代表・橋元良明東京大学教授)、「友だちとはプライベートも含めて密につきあいたい」という回答は、若年層ほど多かった。
そのように親密な関係を求める一方で、彼ら彼女らは相手に負担をかける(あるいはお互いに負担をかけあう)ことには、きわめて敏感だ。その端的な例を、先日たまたま見ていたテレビ番組のワンシーンから、引いておこう。その番組は、男女の若者たちがともに旅するなかで生まれる恋愛模様をドキュメンタリー風に撮影したものなのだが、ある男性が意中の女性に告白した後、こう付け加えたのだ。
「ゴメン、重いかもしれないけど、そういうつもりはないから。重く考えないでね」
彼ら彼女らにとって、愛の告白は相手に負担を強いる「重い」ものなのである。日ごろ大学生と接している私自身の経験から言っても、このような感覚は決して珍しいものではない。「重い」関係は、べったりと相手を(互いを)縛ってしまう。そのことを今の若者たちは何よりも嫌うのである。
こうした「重い」関係を忌避し、さっぱりした「軽い」関係を求める傾向は、日本人全体に高まってきている。NHKが1973年からおこなっている『日本人の意識』調査によれば、職場・親戚・近隣との関係のいずれにおいても、「なにかにつけ相談したり、助け合えるようなつきあい」を望む者は、最近になるほど減少しており、特にその傾向は若年層に顕著に現れている。そうしたなかで、「共話」の作法は、〈私〉のもつ重さを消し、相手に(互いに)負担をかけない関係を織りなそうとする作法としてあるのではないだろうか。
* * *
「共話」の作法は、相手に負担をかけないという配慮のシグナルであるわけだが、一方で、その作法を共有しない年長世代にとっては、過度の配慮に思えて、そのようなシグナルを示されること自体に苛立ちをおぼえてしまう。相手に変な気を遣わず、もっとしっかり〈私〉を主張すればいいではないか、と。大人の社会では、「対話」によって相手を説得し、折りあいをつけていかなくてはならない。「共話」する〈私〉は、そこでやっていくには確かにあまりに頼りなく思えることだろう。
しかし、学校教育・家庭教育のなかで、私たちは、そのような「対話」し、自己主張する〈私〉を、どこまで育もうとしてきただろうか。むしろ、〈私〉を主張することを和を乱すものとして排除し、「個性」すら「協調性」を損なわない範囲で認めてきたにすぎないのではないか。
〈私〉を消し去り、まわりの関係のなかに溶けこむこと。それは実は、これまで日本社会を支えてきた作法でもある。会社に〈私〉を溶けこます「会社人間」などは、そこから生まれてきたのだ。だが、そのような〈私〉を支えてくれていた会社がもはやあてにならないことは、だれの目にも明らかだ。かつての高度経済成長のような、社会的に共有された確固たる目標や価値観があるわけでもない。そのなかにあって、〈私〉を人間関係へ融解させる作法だけが、「協調性」といった美名のもとに取り残されてきた。
そこから、しっかり自己主張する〈私〉が育まれることなど、まさに「ありえない」。私たち大人を戸惑わせる「共話」的なコミュニケーション作法は、皮肉にも、そうした私たちの教育の成果なのかもしれないのである。